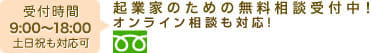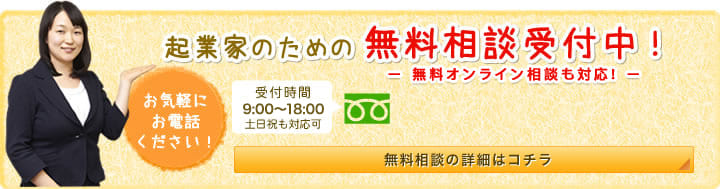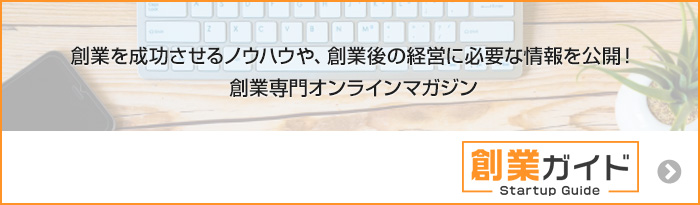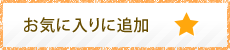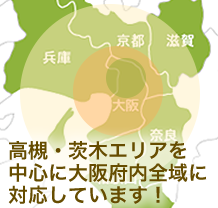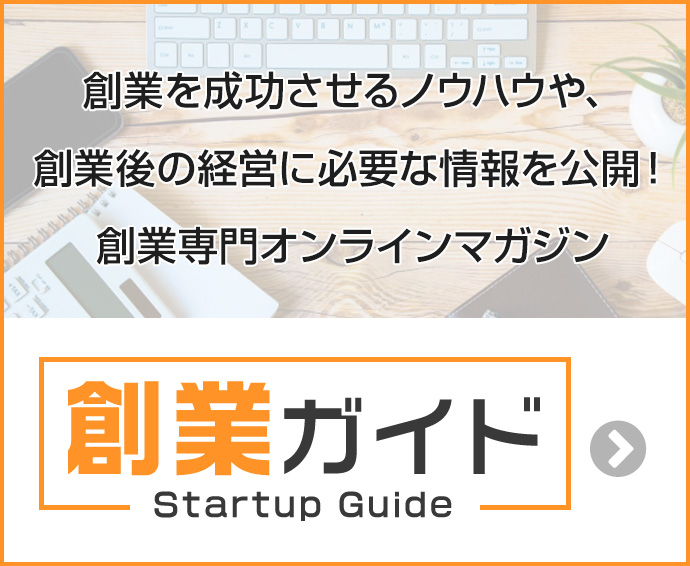【創業支援コラム】20251118 11周年
2025年11月、当事務所は開業から丸11年を迎えました。
11年間、なんとかかんとか生き延びて来られたのはお客様、当事務所メンバー、当事務所に関係していただいている方々のおかげであり、感謝の気持ちでいっぱいです。
いつもありがとうございます。
毎年、この11月のニュースレターでは過去の当事務所の取り組み(失敗事例やそこから学んだこと)を中心にお伝えしていますが、今年も懲りずに同じような内容をお伝えさせていただきます。
1.開業前
・サラリーマンとして、超絶ブラック勤務をしていたため、何となく頭の中で開業の事業計画を作る以外は特段の準備をすることなく、税理士業務については顧客ゼロ、人脈ゼロ、税理士業務のブランク7年、個人の貯金数十万円という状況でスタート。
・さすがに事業資金がないので、開業してすぐに日本政策金融公庫から500万円を借入
・開業前に考えた事業計画は、メインの集客方法は人と会ってお客様を紹介してもらうという方法で、サブの集客方法はホームページ(以下、HP)を作って、広告をかけて集客する方法を考えていました。
2.開業1,2年目(2014~2016年)
・早速、人と会ってお客様の紹介を受けようと思い、交流会などに出席するものの、2ヶ月で挫折。
・毎日のようにたくさんの人と会うのは、私にはしんどかったです…
・一方で、サブで考えていたHP集客は、お客様になって欲しい人を絞り込んで広告をかけて、当事務所に興味がある方から連絡をいただくという流れなので、自分にはピッタリの方法でした。
【学び】何か一つの方法だけに頼るのではなく、常に代替方法も用意しておくと安心感が増す
・そして、HPの集客に注力したところ、幸運にも毎月多数の方々からお問い合わせをいただくことができました。
・売上がゼロだったので、売上を上げようと日本政策金融公庫から借りた 500万円を元手に毎月何十万と広告に注ぎ込んで集客実施。
・その結果、毎月新規でお客様が数人増加するものの、売上の増加は毎月数万円。よって、 「売上▲広告費=大赤字」かつ「売上▲広告費▲諸経費▲廣岡の最低限の生活費=もっと大赤字」となり、借りた500万円が半年後に100万円以下となり、そのときに資金繰り不安から「人生初の10円ハゲ」になりました。
→サラリーマン時代の超絶ブラック勤務では10円ハゲにならなかった
【学び】創業時はもちろんのこと、常にお金は潤沢に持っていた方がいいです(理想は1年間の固定費の半年から1年分のお金を持つ)。自己資金でお金を持とうとしても時間がかかるため、金融機関から借りられる時に借りておくのがいいと考えます。 ただし、無駄遣いしない人限定です。
・この広告費への(過剰?)投資によって自己資金が500万が100万円を切ったあと、幸運にも開業から2か月間頑張った「人と会う活動」でのつながりから、公的機関や金融機関からコンサルティングの仕事を紹介いただけたため、なんとか税理士業務の赤字を埋めることができました。
【学び】行動し続けていれば、あとから何らかの結果がついてくることがある
・開業1,2年目は税理士業務の売上アップのための赤字を補填するために、コンサルの仕事を詰め込むという状況のため、寝る時間以外(1日14時間程度)は働いていました。
→もし、今のあなたが同じ状況にあればしばらく頑張りましょう
【学び】
・事業を軌道に乗せるまではワークライフバランスという言葉は無視していいと考えます(健康に影響が出ない程度。睡眠時間だけは確保必須)。
・理想は最初から自分が望む労働時間で、自分が望む給与がもらえるくらいの利益を稼げることですが、それは開業直後は無理な人が大半です(そんなことができるノウハウや資産等を持っていないことが大半のため)。
・開業直後の人が持っている最大の資産である「時間」を使って、非効率・非合理な行動をしながら、その行動を改善して、徐々に効率化していくのがベターだと考えます。
3.開業3~5年目(2017~2019年コロナ前)
・そんなこんなで開業3年目(2017年)になると売上・資金繰りは少しだけ安定してきた結果、私の生産キャパはほぼ埋まりました(追加で新規売上を作るのが難しい状態)。
・でも開業直後に、お金が減っていった記憶があるため、どうしても売上を増やそうという思いから茨木支店開設(受注したあとの生産は根性でなんとかなると思っていた)。
・そして、茨木支店を開設して受注は増えるものの、さらに廣岡の生産キャパが埋まっていき、大変ありがたいことと思いつつも、「もうこのままだと続けられない」と思い、茨木支店は半年で撤退。
【学び】開業時の資金繰り不安から必死のパッチで売上・利益の増加を目指すのは良いことですが、最低限の生活費を確保できるようになり、かつ、社長(創業者)の生産キャパが埋まっていれば、単純に売上増加を目指すことから立ち止まって考える必要があります。
当時を振り返ったときに、本当は何をすれば良かったかと言うと、
・まずは、自分の会社を将来どうしたいかを考える(自分一人もしくは少人数の規模を目指すのか、それとも規模を増やし続けたいのか)
ことが大事です。
①自分一人もしくは少人数の規模を目指す場合に何をすればいいか
・社長の生産キャパが埋まっているため、まずは既存得意先のうち、不採算(自分の理想の利益が取れていない状態)の得意先から値上げを実施(仮に不採算の得意先との取引がなくなっても社長の生産キャパが空いて、利益が取れる新規得意先を受注できる余地が生まれるため失うものがない)
・次に、不採算の既存得意先の値上げと同タイミングで新規見込客へ提示する料金の値上げ(自分の理想の利益よりも更に値上げ)を実施(社長の生産キャパが埋まっているため、受注していいのは今よりも利益が取れる新規客のみ)
・不採算の既存得意先の値上げ、新規見込客へ提示する料金の値上げができれば、そのあとは社長の生産キャパの様子をみながら、生産キャパが埋まりそうであれば、低採算得意先(理想の利益が取れているか微妙な得意先)の値上げを実施
・あとは、社長の理想とする労働時間や利益を鑑みて、新規客の受注停止や新規客・既存得意先の更なる値上げを実施していくのがいいです。
・これを続けることで、社長の理想とする労働時間や利益がでる事業ができると思います。
②規模を増やし続けたい場合に何をすればいいか
・まずは不採算得意先の値上げを実施するのが理想だと考えます(ただし、規模を大きくしたいので、売上が下がる可能性があることに抵抗感が大きいと思う)
→当事務所はここができなかった…
・上記ができれば、社長の最低限の生活費が確保できて、かつ生産キャパが埋まりそうな半年前に人材採用や外注化を検討するのがいいです(でも、そんな前もって準備はできないので、大半の方が社長の生産キャパが埋まってから人材採用等を進めることになると思います)。
→これも当事務所はできなかった…
・最初は何も考えずに、自分の仕事をやってほしいとの思いから、会計事務所の経験者を採用。
・採用したはいいものの、「仕事をどうやって進めるか」という手順書はなく、廣岡も外出が多いため、「分からないことはとりあえず自分で考えてやっておいて」という放置プレイ。
・結果として、採用してもすぐやめていきました(2人連続で1ヶ月以内に退職)
【学び】深く考えずに採用活動をしても全く上手くいかない
・その経験から、どんな人が入社しても、廣岡の指示がなくても一定レベルで仕事が進めることができるように手順書を作成(通常の仕事で埋まっている上に手順書作成の時間も加わり月300時間超労働)。
・また、活躍する人材に入社していただきたいので、採用時点の人の見極めのハードルを高くするために適性検査を導入。
→詳しくは前月25/10月号のニュースレター参照
・これにより、会計事務所経験者でなくても、人柄がよく、やる気があって、能力が高い人を募集して採用することができるようになり、徐々にメンバーも増加。
・結果、2018~19年にかけて私の仕事をどんどんとメンバーに移行し、その空いた時間で生産効率を上げようと考え、「資料のデータ化」「社内外のコミュニケーションをチャット(今、使っていただいているチャットワーク)に移行」「生産計画」「工数管理」などの仕組みを作っていきました。
4.2020年~2025年現在
・「このままずっと順調に行けるかも」と思っていたのですがコロナ禍突入。
・2020年、コロナ流行により一番影響があったのが当社の一番集客の柱だったHP集客です。 コロナによって、WEBで集客する競合が増え、かつ、競合ではなかったマネーフォワードやfreeeもWEBで積極的に広告宣伝し始めたため、当事務所のHP集客が激減…
・開業時から続けていたもう一つの集客媒体であるDMを強化しようと考え、商品を変えて、DMエリアを拡大することによって、幸運にもHP集客の減少をカバーできました。
【学び】集客媒体は1つに絞らずに、常に複数個持っておいた方がいい
・以後、集客方法の開発を1年に複数個ペースで実施して、1個がダメでも、他の方法があるという状態を作ろうとしてます
・もう一つ、開業からは税理士事業とは別にコンサル事業もやってきたのですが、コロナの影響で簡単に融資や補助金が出たために受注が減少
・コンサル事業の時間の減少分を税理士事業に充てることで、コンサル事業の売上減少分を賄うことができた
【学び】理想的には、事業は複数あった方がいい
★現在、既存事業が1つで、かつ、利益が潤沢に出ていない場合に新規事業に取り組むのはお勧めしないです(新規事業開発は数年間は大赤字になる可能性が高く、かつ、うまく事業が立ち上がるか不透明なため)
→まずは得意先数を増やして少数の得意先に依存しない体制を作り、その上で集客経路を複線化することをお勧めします。
・メンバーとはコロナ前から1か月に1度の面談(社内では1on1MTGと呼んでいます)をして、メンバーが何に困っているか等を把握
・コロナ禍で完全在宅勤務体制に移行したため、1か月に1度の1on1MTGだけではメンバーの様子がよく分からない状態になり、決算書みたいに数値でメンバーの状況を把握したいと考え、エンゲージメントサーベイを導入(当事務所はwevoxを利用)することで、メンバーのことがよく分からないという不安を少しだけ軽減できました。
・なんとかかんとかコロナ禍もやってこれたのですが、25/9月号のニュースレターでお伝えした通り、2024年からgoogleのAI overview導入でさらにHP集客が減少し、かつ2025年からDM集客も原因不明の激減。
・まずはDM改善に取り組み、現状は何とか元に戻った状態となっています。
【学び】時間の経過とともに、競合や社会環境の変化に伴い事業が悪化するので、原因分析と改善をやり続けないと現状維持すらできない。
毎年、色々な出来事がありますが、これからも様々なことにチャレンジして、その反省や学びをあなたと共有することで、少しでもあなたのお役に立てればと思っております。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
高槻の税理士による創業支援コラムの最新記事
- 【創業支援コラム】20260219 能力に頼らない
- 【創業支援コラム】20260119 情報の仕入
- 【創業支援コラム】20251215 2025年プライベートの振り返り
- 【創業支援コラム】20251025 追肥と人材採用
- 【創業支援コラム】20250918 サーフ
- 【創業支援コラム】20250820 胃カメラリベンジ
- 【創業支援コラム】20250711 いちごモニタリング
- 【創業支援コラム】20250620 自動販売機のPDCAサイクル
- 【創業支援コラム】20250520 再チャレンジ
- 【創業支援コラム】20250415 ハンバーガーの自動販売機
- 【創業支援コラム】20250316 胃カメラ
- 【創業支援コラム】20250219 電気カーペットとPDCAサイクル
- 【創業支援コラム】20250123 ヒラメ×謹賀新年
- 【創業支援コラム】20241222 エンゲージメントサーベイ
- 【創業支援コラム】20241119 10年間の歩み(反省と学び)
- 【創業支援コラム】20241015 はんだごて
- 【創業支援コラム】20240916 海上アスレチック
- 【創業支援コラム】20240827 棒をつかむ
- 【創業支援コラム】20240713 アヒージョと怪獣8号
- 【創業支援コラム】20240617 船酔い対策の効果検証
- 【創業支援コラム】20240513 フィールドアスレチック
- 【創業支援コラム】20240415 ヤメルからハジメル
- 【創業支援コラム】20240318 肘×ギガデイン
- 【創業支援コラム】20240222 新たな経営者保証不要の融資制度
- 【創業支援コラム】20240114 温泉PDCAサイクル
- 【創業支援コラム】20231218 2023年振り返り
- 【創業支援コラム】20231125 9周年
- 【創業支援コラム】20231022 とある地方の花火大会
- 【創業支援コラム】20230917 オニヤンマくんとインボイス
- 【創業支援コラム】20230825 とうとう〇〇になりました
- 【創業支援コラム】20230720 ウーパールーパー
- 【創業支援コラム】20230622 エメラルドグリーン
- 【創業支援コラム】20230513 虫歯
- 【創業支援コラム】20230422 正しい頭の洗い方
- 【創業支援コラム】20230314 経営者保証改革プログラム
- 【創業支援コラム】20230218 ハイボール39円と値決め+原価計算
- 【創業支援コラム】20230120 ヒアリングの重要性
- 【創業支援コラム】20221222 食卓の進化と非ルーティンのルーティン化
- 【創業支援コラム】20221118 8周年
- 【創業支援コラム】20221020 アオリイカと新規事業開発
- 【創業支援コラム】20220916 Fortnite
- 【創業支援コラム】20220820 山へ〇〇に行きました
- 【創業支援コラム】20220810 インボイス制度 ー最終回 インボイス制度の経過措置等ー
- 【創業支援コラム】20220716 インボイス制度 -第3回 あなたの事業の仕入先等に対する対応の仕方-
- 【創業支援コラム】20220711 インボイス制度 -第2回 今後、あなたがすべきことは何か?-
- 【創業支援コラム】20220706 インボイス制度 -第1回 概要-
- 【創業支援コラム】20220617 第一次スズメバチ大戦
- 【創業支援コラム】20220501 鰯&鰯
- 【創業支援コラム】20220401 リップスティック
- 【創業支援コラム】20220317 ペーパードライバー
- 【創業支援コラム】20220214 カーテンとジャムの法則
- 【創業支援コラム】20220116 魚釣りと新規事業開発
- 【創業支援コラム】20211214 創意工夫のその先に
- 【創業支援コラム】20211125 7周年
- 【創業支援コラム】20211015 自動販売機とポジショニング
- 【創業支援コラム】20210922 あなたの経験すべてがビジネスになる
- 【創業支援コラム】20210823 困難から逃げない
- 【創業支援コラム】20210721 まずは始めて、そして小さな改善を積上げよう
- 【創業支援コラム】20210620 成果への梯子のかけ方
- 【創業支援コラム】20210511 プロセスエコノミー
- 【創業支援コラム】20210417 卒園式
- 【創業支援コラム】20210326 考える時間の重要性
- 【創業支援コラム】20210219 進捗管理の重要性
- 【創業支援コラム】20210119 大掃除
- 【創業支援コラム】20201218 ゲームの世界
- 【創業支援コラム】20201123 6周年
- 【創業支援コラム】20201021 思った通りにならない≒成長
- 【創業支援コラム】20200921 選択と集中の怖さを知る
- 【創業支援コラム】20200906 何でも楽しくやるために
- 【創業支援コラム】20200731 パンクから学ぶマインドの重要性
- 【創業支援コラム】20200717 環境の変化×勝男
- 【創業支援コラム】20200612 継続的な小さな改善が大きな改善につながる
- 【創業支援コラム】20200517 変化に対応することの重要性
- 【創業支援コラム】20200416 チャンスはピンチの顔をしてやってくる
- 【創業支援コラム】20200406 金融機関との付き合い方
- 【創業支援コラム】20200326 緊急時、どのように対処するか
- 【創業支援コラム】20200319 長期的な人生・仕事の目的達成に必要なこと
- 【創業支援コラム】20200227 社長は事業の中で一番大事なことをする
- 【創業支援コラム】20200124 市場や競合の環境は常に変化し続ける
- 【創業支援コラム】20191223 ポケカ×脳の快楽
- 【創業支援コラム】20191214 あっという間に・・・
- 【創業支援コラム】20191130 五周年
- 【創業支援コラム】20191121 ロードバイク×PDCAサイクル
- 【創業支援コラム】20191022 ダブルチェックの原則
- 【創業支援コラム】20191011 ゼロワンプロジェクト
- 【創業支援コラム】20190923 小さな困難から逃げない
- 【創業支援コラム】20190916 必要性=行動の源
- 【創業支援コラム】20190825 ビジョンを描くこと×モリ
- 【創業支援コラム】20190820 市場の変化×おもちゃ屋さん
- 【創業支援コラム】20190807 ノーサイドゲーム
- 【創業支援コラム】20190716 成長戦略と毛虫
- 【創業支援コラム】20190705 人との出会い
- 【創業支援コラム】20190607 徒競走とは
- 【創業支援コラム】20190516 大きな気づきを得るために必要なこと
- 【創業支援コラム】20190507 PDCAサイクルのCとA
- 【創業支援コラム】20190417 リサーチの重要性
- 【創業支援コラム】20190406 「やめる」から「はじめる」
- 【創業支援コラム】20190331 精神と時の部屋
- 【創業支援コラム】20190204 市場の変化は速い
- 【創業支援コラム】20190128 在庫管理の重要性
- 【創業支援コラム】20181105 人が成長するには・・・
- 【創業支援コラム】20181002 ビジョン×ザ・鉄腕ダッシュ
- 【創業支援コラム】20180919 判断力の磨き方
- 【創業支援コラム】20180901 現状維持バイアス×期日設定
- 【創業支援コラム】 20180817 少し高い目標を設定すること
- 【創業支援コラム】20180809 夏祭りの夜店 → コト消費
- 【創業支援コラム】20180730 マーケット調査の重要性について
- 【創業支援コラム】 20180718 日常トライアングルから非日常へ
- 【創業支援コラム】20180705 サッカーワールドカップ
- 【創業支援コラム】20180608 ピカチン大百科
- 【創業支援コラム】20180525 人類誕生 第2段
- 【創業支援コラム】20180510 ホームステイ×ベンチマーク
- 【創業支援コラム】20180427 オシマイダー
- 【創業支援コラム】20180406 ニジゲンノモリ×フロント・バックエンド商品
- 【創業支援コラム】20180330 気づきは比較からはじまる
- 【創業支援コラム】20180324 確定申告終了のホイッスルがなりました
- 【創業支援コラム】20180309 シーザーサラダの気づき
- 【創業支援コラム】20180223 マグロ×マインドセット
- 【創業支援コラム】20180213 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
- 【創業支援コラム】20180205 いい組織をつくるために
- 【創業支援コラム】20180110 正月とオセチと私
- 【創業支援コラム】20171228 男の勲章
- 【創業支援コラム】20171221 1年の振り返り(プライベート)
- 【創業支援コラム】20171123 補欠に回りました。。。
- 【創業支援コラム】20171123 ~よーいドン!~
- 【創業支援コラム】20171119 ~しちごさん~
- 【創業支援コラム】20171112 ~ HAPPY BIRTHDAY ~
- 【創業支援コラム】20171102 ~授業参観~
- 【創業支援コラム】20171025 ~〇〇デント~
- 【創業支援コラム】20171013 ~あれもこれも~
- 【創業支援コラム】20171006 ~経営って何なん?~
- 【創業支援コラム】20170929 ~事業が立ち上がりやすい人、立ち上がりにくい人~
- 【創業支援コラム】20170922 ~事業を立ち上げることは難しい・・・~
- 【創業支援コラム】20170915 ~企業の生存率~
- 【創業支援コラム】20170831 ~事業の横展開~
- 【創業支援コラム】20170823 ~かき氷屋のエリア戦略~
- 【創業支援コラム】20170803 ~経営のことだけを考える時間~
- 【創業支援コラム】20170727 ~量が質に転化する~
- 【創業支援コラム】20170720 ~返報性の原理~
- 【創業支援コラム】20170713 ~継続することは難しい~
- 【創業支援コラム】20170629 好奇心の果て
- 【創業支援コラム】20170620 運動会の進化論
- 【創業支援コラム】170613 ~チャドクガ~
- 【創業支援コラム】20170607 ~昔とった杵柄~
- 【創業支援コラム】20170530~あの季節がやってきた~
- 【創業支援コラム】20170525 ~ウマズラハギノキモ~
- 【創業支援コラム】20170519 8本
- 【創業支援コラム】20170515 レンタル農園
- 【創業支援コラム】20170501 子どもの入学式
- 【創業支援コラム】20170131 客単価を上げるために
- 【創業支援コラム】20150125 創業時はどのような資金調達先があるか?
- 【創業支援コラム】20150118 起業する際のお金の重要性